「走行中にいきなりエンジンが止まった」
「警告灯が何度もついて不安になる」
「修理の見積もりが高額で驚いた」
など、三菱ふそうのキャンターについて、このような悩みや不安を抱えていませんか。
本記事では、キャンターが故障しやすいといわれる理由から、具体的な故障事例、修理費用、そして長く乗り続けるためのメンテナンス方法までを解説します。
この記事を読むことで、キャンターの故障について深く知ることができ、安心して購入や売却、そして日々の運転ができるようになります。
記事のポイント
- 故障の噂は特定のエンジン(4P10)に集中
- DPF・インジェクターの不具合が多発
- 修理費用は高額になる可能性
- 日常メンテナンスで故障リスクは低減可能
- 古いモデルでも海外需要で高価売却が狙える
\損する前にご相談を/
修理不要|トラック高価買取専門店おすすめ
| おすすめ トラック買取専門店 | |
|---|---|
1位.トラックファイブ \創業22年の大手/ 今すぐ無料査定 | ◆ 圧倒的な高価買取 直営店で中間マージンなし。海外販路が強く円安効果も反映 ◆ 国内大手の信頼 年間買取13,000台以上。リピート率47.2% ◆ スピード対応 最短即日現金化も ◆ どんな車も査定OK 低年式、不動車、故障車も対応 ◆ 安心のサポート 面倒な書類手続きもすべて無料で代行 |
2位.Bee Truck \プロの加点査定/ 今すぐ無料査定 | ◆ 直販型で高価買取 整備から販売まで自社完結。オークション任せにしない ◆ 独自の加点査定 業界歴20年以上の査定士が担当。他社が見落とすポイントも徹底評価 ◆ 再生し価値アップ 自社整備工場で修理・塗装。原価以上の価値を生み出す ◆ 他社見積り歓迎 比較前提の戦略で1円でも高く買取り |
3位.トラック王国 \満足度93%/ 今すぐ無料査定 | ◆ 現地での減額なし 電話ヒアリングと相違なければ、査定額を保証 ◆ お客様満足度93% 創業17年の実績 ◆ 最短即日現金化 会社の運転資金ニーズにも対応 ◆ 柔軟な要望に対応 「社名ペイントをすぐ消してほしい」「書類手続きを代行してほしい」など ◆ 高い知名度 見たことある安心感 |
査定額は1社ごとに全く違います。何十万円も損しないためにも、3社査定をしましょう
三菱ふそうのキャンターは「故障が多い」「壊れやすい」のは本当か?
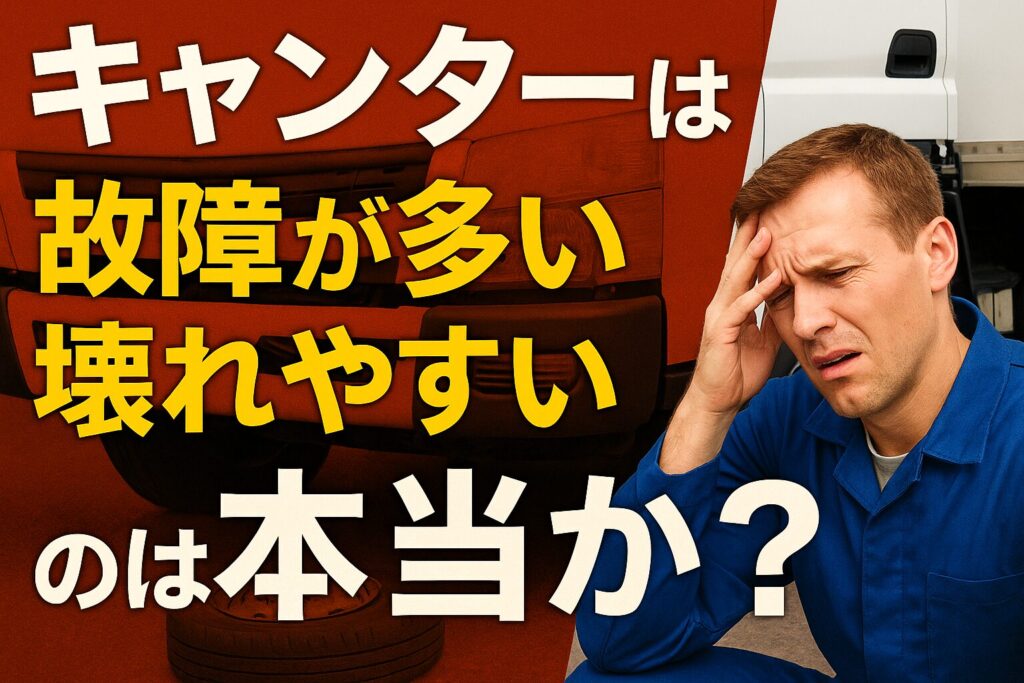
三菱ふそうのキャンターが「故障が多い」「壊れやすい」という評判は、一部のモデルにおいて事実といえます。
特に2010年以降に登場した、特定のエンジンを搭載したモデルで不具合の報告が集中している傾向です。
- 結論:特定のモデル・エンジンに注意が必要
- オーナーからの評判
- 他社トラックとの比較
全てのキャンターが壊れやすいわけではなく、問題点を正しく理解することが重要になります。
それでは、キャンターの信頼性について、さまざまな角度からくわしく見ていきましょう。
結論:特定のモデル・エンジンに注意が必要
キャンターが故障しやすいという評判は、主に第8世代モデルに搭載された「4P10」エンジンに起因します 。
このエンジンは、当時の厳しい排出ガス規制に対応するため、非常に複雑な構造をもっていました。
- 第8世代(ブルーテックキャンター)に多い
- 排出ガス浄化装置の不具合が中心
- エンジン制御システムの複雑化
結果として、エンジン本体や関連する電子制御部品、排出ガス浄化装置などでトラブルが多発する原因となりました。
古い世代のキャンターや、異なるエンジンを搭載したモデルでは、評判が大きく異なります。
オーナーからの評判
実際のオーナーからの評判は、良い評価と悪い評価の両方が見られます。
パワーがあり運転しやすい、小回りが利くといった肯定的な意見も少なくありません 。
- パワーや運転のしやすさは高評価
- 警告灯の頻繁な点灯に不満の声
- 修理費用が高額になりやすい
一方で、「警告ランプが直ぐにつく」「保証が切れたとたんに高額な修理が続いた」といった声も多く挙がっています 。
特に修理費用の高さが、ユーザーの満足度を下げる一因となっているようです。
他社トラックとの比較
キャンターに限らず、現代のディーゼルトラックはどのメーカーも複雑な排出ガス浄化装置を搭載しています。
そのため、他社のトラックでも同様のシステムに起因する故障は報告されています 。
- いすゞ「エルフ」は信頼性が高いと評判
- 日野のエンジンにも特有の故障事例あり
- UDトラックスも部品が高額な傾向
例えば、日野のトラックでは噴射ポンプの不具合が、UDのトラックではオルタネーターの故障などが知られています 。
トラックの故障は、メーカーごとの設計思想や技術的な特徴によって傾向が異なります。
キャンターに「故障が多い」といわれる背景

キャンターに故障が多いといわれるようになった背景には、技術的な要因と規制強化が深く関わっています。
特に「4P10」エンジンの導入が、大きな転換点となりました。
- 複雑化した「4P10エンジン」の導入
- 厳しい排出ガス規制への対応
- 部品間の「負の連鎖」
これらの要因が重なり合うことで、特定のモデルで故障が頻発する状況が生まれたのです。
それぞれの背景について、くわしく解説していきます。
複雑化した「4P10エンジン」の導入
不具合報告の中心にある4P10エンジンは、イタリアのフィアット社と共同開発されたものです 。
このエンジンは、日本のトラック市場で「不具合NO.1」とまでいわれるほど、多くのトラブルを抱えていました 。
- フィアット社との共同開発エンジン
- 電子部品にはボッシュ社製を採用
- 一度に8〜10項目のエラーコードが出ることも
高性能化と引き換えに構造が非常に複雑になり、診断や修理が困難なケースが少なくありません。
特にエンジン制御と燃料噴射システム、排出ガス浄化装置の連携が、トラブルの温床となったのです。
厳しい排出ガス規制への対応
2010年頃から強化された排出ガス規制(ポスト新長期規制)への対応が、トラックの構造を大きく変えました。
キャンターも例外ではなく、DPFや尿素SCRシステム(BlueTec)といった高度な浄化装置の搭載が必須となったのです 。
- DPFによるPM(粒子状物質)の捕集
- 尿素SCRによるNOx(窒素酸化物)の分解
- 多数のセンサーによる電子制御
これらの装置は、環境性能を飛躍的に向上させましたが、同時に新たな故障リスクを生み出しました。
特に煤(すす)の詰まりやセンサーの故障が、エンジンの不調に直結するケースが多発しています。
部品間の「負の連鎖」
キャンターの故障で特に厄介なのが、部品間で発生する「負の連鎖」です 。
ひとつの部品の不具合が、次々と他の部品の故障を誘発する現象を指します。
- インジェクターの不具合がDPFの詰まりを誘発
- DPFの詰まりがエンジン不調の原因に
- 複数の警告灯が同時に点灯し原因特定が困難
例えば、インジェクターの噴射精度が落ちると不完全燃焼が起こり、DPFに大量の煤が溜まります 。
その結果、DPFの警告灯が点灯し、最終的にはエンジン本体にまでダメージが及ぶという悪循環に陥るのです。
キャンターの「よくある故障と対策」

キャンター、特に4P10エンジン搭載モデルで報告される故障には、いくつかの典型的なパターンがあります。
ここでは、特に多い3つの故障事例と、それぞれの基本的な対策について解説します。
- エンジン関連の故障(4P10エンジン)
- DPF(排出ガス浄化装置)の詰まり
- インジェクターの不具合
これらの故障は互いに関連していることが多いため、症状が出たら早めに専門家へ相談することが大切です。
それでは、具体的な故障内容と対策をくわしく見ていきましょう。
エンジン関連の故障(4P10エンジン)
4P10エンジンで最も深刻なトラブルのひとつが、走行中のエンジンストール(エンジン停止)です 。
原因は多岐にわたりますが、主に燃料系統、電気系統、インジェクターの不具合が考えられます 。
- 燃料ポンプの不具合による燃料供給不足
- 燃料ポンプのカプラー溶損による接触不良
- タイミングチェーンの破損によるエンジン停止
特に燃料タンク上部にあるポンプのカプラーが熱で溶けて接触不良を起こす事例は、多く報告されています 。
対策としては、定期的な点検と、異常を感じたらすぐに走行を中止し、点検を依頼することが不可欠です。
DPF(排出ガス浄化装置)の詰まり
DPFの警告灯の点灯も、キャンターで非常に多いトラブルのひとつです 。
警告灯が「点滅」している段階であれば、手動再生で煤を除去できる可能性があります 。
- 警告灯の点滅は手動再生のサイン
- 警告灯の点灯はエンジン出力が制限される
- 放置するとエンジン警告灯も点灯する
しかし、点滅を無視して走行を続けると警告灯が「点灯」に変わり、エンジンの出力が時速40〜50km程度に制限されます 。
この状態になると整備工場での強制再生が必要になるため、警告灯が点滅したら速やかに安全な場所で手動再生を行いましょう 。
インジェクターの不具合
エンジンの不調やDPFの詰まりの根本的な原因となっていることが多いのが、インジェクターの不具合です 。
インジェクターは燃料を霧状に噴射する精密部品で、劣化するとさまざまな問題を引き起こします 。
- 加速時に失速してエンジンが停止する
- エンジンから異音(ガラガラ音)がする
- 排気ガスから黒煙が出る
インジェクターが詰まったり、正常に作動しなくなったりすると、不完全燃焼を起こしてDPFを詰まらせる原因になります。
定期的な燃料添加剤の使用や、専門業者による洗浄が、インジェクターの寿命を延ばすための有効な対策です 。
キャンターの「修理費用(概算)」

キャンターの修理費用は、故障箇所によっては非常に高額になる可能性があります。
特にエンジンや排出ガス浄化装置など、主要な部品の交換が必要になると、100万円を超えるケースも珍しくありません 。
- エンジン関連の修理費用
- DPF・インジェクターの修理費用
- その他の高額修理費用
ここでは、主な故障箇所の修理費用について、概算の金額を紹介します。
実際の費用は車両の状態や依頼する整備工場によって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
エンジン関連の修理費用
エンジン関連の修理は、キャンターの修理の中でも特に高額になりがちです。
タイミングベルトの破損などが原因でエンジン本体の載せ替えが必要になった場合、120万円もの請求があったという事例もあります 。
- エンジン載せ替え:約120万円〜
- エンジンオーバーホール:約50万円〜200万円
- サプライポンプ交換:約10万円〜
ディーラーでの修理は高額になる傾向があるため、専門の整備工場やリビルト部品(再生部品)の活用も検討するとよいでしょう 。
ただし、リビルト部品を使う場合でも、工賃を含めると数十万円の費用がかかることを覚悟しておく必要があります。
DPF・インジェクターの修理費用
DPFやインジェクター関連の修理費用も、決して安くはありません。
DPFの詰まりを解消するための強制再生や洗浄作業だけでも、数万円の費用がかかります 。
- DPF強制再生・洗浄:約5万円〜
- インジェクター交換(4本):約20万円〜30万円
- 尿素タンクセンサー交換:約20万円
インジェクターの交換は、部品代と工賃を合わせると4本で20万円以上になることもあります 。
DPFの故障はインジェクターが原因であることも多いため、同時に点検・修理を行うとさらに費用はかさみます。
その他の高額修理費用
エンジンやDPF以外にも、高額な修理費用が発生する可能性のある箇所は存在します。
例えば、クラッチのオーバーホールでは約20万円、事故などでフレーム修正が必要になると100万円を超えることもあります 。
- クラッチオーバーホール:約19万5,000円
- フレーム修正:約130万円
- キャビン(運転台)載せ替え:約55万円〜(中古部品の場合)
また、運転台であるキャビンを交換する場合、中古部品を使っても工賃込みで55万円以上かかる可能性があります 。
トラックは乗用車に比べて部品ひとつひとつが高価なため、日頃のメンテナンスがより重要になります。
\損する前にご相談を/
修理不要|トラック高価買取専門店おすすめ
| おすすめ トラック買取専門店 | |
|---|---|
1位.トラックファイブ \創業22年の大手/ 今すぐ無料査定 | ◆ 圧倒的な高価買取 直営店で中間マージンなし。海外販路が強く円安効果も反映 ◆ 国内大手の信頼 年間買取13,000台以上。リピート率47.2% ◆ スピード対応 最短即日現金化も ◆ どんな車も査定OK 低年式、不動車、故障車も対応 ◆ 安心のサポート 面倒な書類手続きもすべて無料で代行 |
2位.Bee Truck \プロの加点査定/ 今すぐ無料査定 | ◆ 直販型で高価買取 整備から販売まで自社完結。オークション任せにしない ◆ 独自の加点査定 業界歴20年以上の査定士が担当。他社が見落とすポイントも徹底評価 ◆ 再生し価値アップ 自社整備工場で修理・塗装。原価以上の価値を生み出す ◆ 他社見積り歓迎 比較前提の戦略で1円でも高く買取り |
3位.トラック王国 \満足度93%/ 今すぐ無料査定 | ◆ 現地での減額なし 電話ヒアリングと相違なければ、査定額を保証 ◆ お客様満足度93% 創業17年の実績 ◆ 最短即日現金化 会社の運転資金ニーズにも対応 ◆ 柔軟な要望に対応 「社名ペイントをすぐ消してほしい」「書類手続きを代行してほしい」など ◆ 高い知名度 見たことある安心感 |
査定額は1社ごとに全く違います。何十万円も損しないためにも、3社査定をしましょう
キャンターの故障を減らすための「日常メンテナンス」

キャンターの故障リスクを減らし、長く乗り続けるためには、日々のメンテナンスが非常に重要です。
特にDPFやエンジンに関するトラブルは、運転の仕方やオイル交換などで予防できる部分も多くあります。
- DPFの詰まりを防ぐ運転を心がける
- DPF警告灯の正しい対処法
- エンジンオイルと燃料添加剤の活用
ここでは、オーナー自身が実践できる日常的なメンテナンスのポイントを3つ紹介します。
少しの心がけで、高額な修理費用を未然に防ぐことにつながります。
DPFの詰まりを防ぐ運転を心がける
DPFに煤が溜まる主な原因は、排気ガスの温度が上がらない短距離走行や長時間のアイドリングです 。
DPFは排気ガスの熱を利用して煤を燃焼させるため、エンジンに負荷をかける運転が定期的に必要となります。
- 短距離走行やチョイ乗りを避ける
- 長時間のアイドリングは控える
- 定期的に高速道路などを走行しエンジンを回す
AT車の場合は、マニュアルモードなどを活用してエンジン回転数を高めに保って走行するのも効果的です 。
日々の業務の中で、意識的にエンジンに負荷をかける時間をつくることが、DPFの健康を保つ秘訣です。
DPF警告灯の正しい対処法
DPF警告灯が点滅した場合は、DPFに煤が溜まり始めているサインです 。
この段階であれば、手動再生スイッチを操作することで、溜まった煤を燃焼させることができます。
- 安全な場所に停車しパーキングブレーキをかける
- シフトレバーをニュートラル(AT車はP)に入れる
- DPF再生スイッチを長押しして手動再生を開始
手動再生は通常15分から20分程度で完了し、完了すると警告灯が消灯します 。
もし手動再生ができない場合や、完了してもすぐにまた点滅するような場合は、早急に整備工場で点検を受けてください。
エンジンオイルと燃料添加剤の活用
エンジンオイルの管理は、エンジンの寿命を左右する最も基本的なメンテナンスです。
DPF搭載車には、必ず「DPF対応オイル」を使用する必要があります 。
- DPF対応のエンジンオイルを定期的に交換
- エアフィルターの定期的な清掃・交換
- インジェクター洗浄効果のある燃料添加剤の使用
非対応のオイルを使用すると、DPFを詰まらせる原因となり、高額な修理につながる可能性があります。
また、定期的にインジェクタークリーナーなどの燃料添加剤を使用することも、燃料系統をきれいに保ち、トラブルを予防するのに有効です 。
キャンターの「リコール情報の有無」

三菱ふそうは、キャンターに関して過去に複数のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出ています。
リコールは、設計や製造段階での問題が原因で、安全上または環境保全上の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行われます。
- ブレーキ装置に関するリコール
- エンジン部品(ロッカーアーム)に関するリコール
- ブローバイガス還元装置に関するリコール
所有しているキャンターがリコール対象かどうかは、三菱ふそうの公式サイトや国土交通省のウェブサイトで確認できます。
ここでは、特に大規模だったリコール事例をいくつか紹介します。
ブレーキ装置に関するリコール
2020年12月、キャンターなど約1万7千台を対象に、ブレーキキャリパーに関するリコールが届け出られました 。
前輪ブレーキキャリパーのスライドピンにグリスが塗布されていないものがあり、ブレーキパッドが異常摩耗するおそれがあるという内容です。
- 対象台数:17,482台
- 不具合内容:ブレーキパッドの異常摩耗
- 最悪の場合:ブレーキパッドが脱落する可能性
この不具合により、ブレーキ操作後にブレーキが戻りきらなくなり、最悪の場合はブレーキパッドが脱落する危険性がありました。
改善措置として、スライドピンの点検と、必要に応じてキャリパーやブレーキパッドの交換が行われました。
エンジン部品(ロッカーアーム)に関するリコール
2019年7月には、エンジン内部のロッカーアームという部品の耐久性不足を理由に、約1万4千台のリコールが発表されました 。
製造時の管理が不適切だったため、ロッカーアームが早期に摩耗・破損する可能性があるというものです。
- 対象台数:13,995台
- 不具合内容:ロッカーアームの異常摩耗・破損
- 最悪の場合:異音が発生し走行不能に至る
この不具合が進行すると、エンジンから異音が発生し、最悪の場合は走行不能に至るおそれがありました。
改善措置として、全車両のロッカーアームを良品に交換する対応が取られました。
ブローバイガス還元装置に関するリコール
2018年8月には、延べ26万台以上という非常に大規模なリコールが届け出られました 。
ブローバイガス還元装置のフィルターが詰まり、エンジン内部の圧力が異常に上昇するという不具合です。
- 対象台数:260,000台以上
- 不具合内容:エンジン内圧の上昇によるオイル流入
- 最悪の場合:エンジン破損や火災に至る
この状態を放置すると、エンジンオイルが吸排気系に流れ込み、意図しないエンジン回転数の上昇やエンジン破損、さらには火災に至る危険性がありました。
改善措置として、フィルターの新品交換や吸排気系の点検などが行われました。
キャンターの「修理か売却かの決め手」

高額な修理費用が必要になったとき、「修理して乗り続けるべきか、それとも売却すべきか」は非常に悩ましい問題です。
この判断を下すためには、いくつかの要素を総合的に考慮する必要があります。
- 修理費用と車両の市場価値を比較する
- 年式や走行距離を考慮する
- 今後の使用計画と照らし合わせる
特にトラックの場合は、乗用車とは異なる価値基準が存在するため、慎重な判断が求められます。
ここでは、修理か売却かを決めるためのポイントを解説します。
修理費用と車両の市場価値を比較する
まず基本となるのが、修理にかかる費用と、そのトラックの現在の市場価値を比較することです。
一般的に、修理費用が車両の市場価値を上回る場合は、売却を検討する方が経済的といえます。
- 修理見積もりを複数の業者から取る
- 買取専門業者に現在の査定額を確認する
- 修理後の価値上昇分も考慮に入れる
例えば、査定額が50万円のトラックに100万円の修理費用がかかる場合、修理は得策とはいえません。
ただし、その修理によってトラックの寿命が大幅に延び、結果的に長く使えるのであれば、修理する価値がある場合もあります。
年式や走行距離を考慮する
トラックの年式や走行距離も、重要な判断材料になります。
年式が古く、走行距離もかなり伸びている車両の場合、ひとつの箇所を修理しても、すぐに別の箇所が故障する可能性があります。
- 10年・走行50万kmが一つの目安
- 「故障の連鎖」が起こるリスク
- 部品の供給が終了している可能性
特に古いモデルでは、交換部品の供給が終了しているケースもあり、修理自体が困難になることも考えられます。
将来的に次々と発生するであろう修理費用を考えると、ある程度の年式・走行距離に達した車両は、大きな故障を機に売却するのも賢明な選択です。
今後の使用計画と照らし合わせる
最終的には、そのトラックを今後どのように使っていくかという事業計画が決め手となります。
あと数年は確実に現在の業務で使い続ける必要があるのか、それとも代替車両の導入を検討する余地があるのかを考えましょう。
- あと何年そのトラックを使用する予定か
- 業務内容の変化に対応できるか
- 乗り換える場合の資金計画
もし数ヶ月以内に乗り換えを計画しているのであれば、高額な修理費をかけて延命させるよりも、現状のまま売却した方が合理的です。
逆に、そのトラックでなければ遂行できない特殊な業務がある場合は、費用がかさんでも修理を選択すべきでしょう。
\損する前にご相談を/
修理不要|トラック高価買取専門店おすすめ
| おすすめ トラック買取専門店 | |
|---|---|
1位.トラックファイブ \創業22年の大手/ 今すぐ無料査定 | ◆ 圧倒的な高価買取 直営店で中間マージンなし。海外販路が強く円安効果も反映 ◆ 国内大手の信頼 年間買取13,000台以上。リピート率47.2% ◆ スピード対応 最短即日現金化も ◆ どんな車も査定OK 低年式、不動車、故障車も対応 ◆ 安心のサポート 面倒な書類手続きもすべて無料で代行 |
2位.Bee Truck \プロの加点査定/ 今すぐ無料査定 | ◆ 直販型で高価買取 整備から販売まで自社完結。オークション任せにしない ◆ 独自の加点査定 業界歴20年以上の査定士が担当。他社が見落とすポイントも徹底評価 ◆ 再生し価値アップ 自社整備工場で修理・塗装。原価以上の価値を生み出す ◆ 他社見積り歓迎 比較前提の戦略で1円でも高く買取り |
3位.トラック王国 \満足度93%/ 今すぐ無料査定 | ◆ 現地での減額なし 電話ヒアリングと相違なければ、査定額を保証 ◆ お客様満足度93% 創業17年の実績 ◆ 最短即日現金化 会社の運転資金ニーズにも対応 ◆ 柔軟な要望に対応 「社名ペイントをすぐ消してほしい」「書類手続きを代行してほしい」など ◆ 高い知名度 見たことある安心感 |
査定額は1社ごとに全く違います。何十万円も損しないためにも、3社査定をしましょう
【知らないと損】10年落ちのトラックでも”驚きの高値”がつくワケ

「もう10年以上乗っているし、故障も多いから価値はないだろう」と諦めてしまうのは早計です。
実は、日本で役目を終えた古いトラックが、海外では驚くほどの高値で取引されています 。
- 海外での日本車ブランドへの高い信頼
- 頑丈で修理しやすい構造が人気
- 発展途上国でのインフラ整備需要
特にキャンターのような小型トラックは、多くの国で高い需要があります。
なぜ古いトラックが高く売れるのか、その理由をくわしく解説します。
海外での日本車ブランドへの高い信頼
海外、特にアジアやアフリカなどの新興国では、「日本車=高品質で壊れにくい」という絶大な信頼があります 。
日本国内では過走行とされる10万kmや20万kmといった走行距離も、海外では「まだまだ走れる」と評価されるのです。
- 品質と耐久性への評価
- 日本国内の車検制度による整備状態の良さ
- 豊富な中古部品で修理が容易
日本の車検制度によって定期的にメンテナンスされていることも、車両の状態が良いと判断される一因です 。
そのため、日本では値段がつかないような古いトラックでも、海外のバイヤーは積極的に買い付けています。
頑丈で修理しやすい構造が人気
最新のトラックは電子制御化が進んでいますが、少し前のモデルは構造が比較的シンプルで頑丈です。
整備環境が整っていない地域では、複雑な電子制御システムはかえって修理を困難にするため、シンプルな構造の古いトラックが好まれます 。
- シンプルなディーゼルエンジン
- 電子制御が少なくメンテナンスが容易
- 悪路でも耐えられる強固なフレーム
多少の故障であれば、現地の技術で修理できてしまうため、機械的な信頼性が高いモデルは特に人気です。
日本で故障が多いとされる4P10エンジン搭載車でさえ、海外では修理して使われることがあります。
発展途上国でのインフラ整備需要
経済成長が著しい発展途上国では、道路や建物の建設といったインフラ整備が急ピッチで進んでいます。
そこで必要となるのが、資材を運ぶためのトラックです。
- 建設資材の運搬
- 物流ネットワークの拡大
- 農業や商業での活用
新車のトラックは高価なため、手頃な価格で手に入る日本の中古トラックは、現地の経済活動を支える重要な役割を担っています 。
このような強い需要が、日本国内の中古トラックの買取価格を押し上げているのです。
\損する前にご相談を/
修理不要|トラック高価買取専門店おすすめ
| おすすめ トラック買取専門店 | |
|---|---|
1位.トラックファイブ \創業22年の大手/ 今すぐ無料査定 | ◆ 圧倒的な高価買取 直営店で中間マージンなし。海外販路が強く円安効果も反映 ◆ 国内大手の信頼 年間買取13,000台以上。リピート率47.2% ◆ スピード対応 最短即日現金化も ◆ どんな車も査定OK 低年式、不動車、故障車も対応 ◆ 安心のサポート 面倒な書類手続きもすべて無料で代行 |
2位.Bee Truck \プロの加点査定/ 今すぐ無料査定 | ◆ 直販型で高価買取 整備から販売まで自社完結。オークション任せにしない ◆ 独自の加点査定 業界歴20年以上の査定士が担当。他社が見落とすポイントも徹底評価 ◆ 再生し価値アップ 自社整備工場で修理・塗装。原価以上の価値を生み出す ◆ 他社見積り歓迎 比較前提の戦略で1円でも高く買取り |
3位.トラック王国 \満足度93%/ 今すぐ無料査定 | ◆ 現地での減額なし 電話ヒアリングと相違なければ、査定額を保証 ◆ お客様満足度93% 創業17年の実績 ◆ 最短即日現金化 会社の運転資金ニーズにも対応 ◆ 柔軟な要望に対応 「社名ペイントをすぐ消してほしい」「書類手続きを代行してほしい」など ◆ 高い知名度 見たことある安心感 |
査定額は1社ごとに全く違います。何十万円も損しないためにも、3社査定をしましょう
キャンターの中古を買うときの「注意点」

キャンターの中古車を購入する際は、故障のリスクを避けるために、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。
特に故障が多いとされるモデルを選ぶ場合には、車両の状態を慎重に見極めることが不可欠です。
- エンジンの状態を入念にチェックする
- 修復歴の有無と車両の使用歴を確認する
- 試乗して走行フィーリングを確かめる
信頼できる販売店を選ぶことはもちろん、自分自身でもある程度の知識を持って車両を確認することが、後悔しない中古車選びにつながります 。
ここでは、具体的なチェックポイントを解説していきます。
エンジンの状態を入念にチェックする
中古キャンター選びで最も重要なのが、エンジンの状態確認です 。
特に4P10エンジン搭載車の場合は、細心の注意を払う必要があります。
- エンジン始動時の異音や白煙の有無
- エンジンオイルの漏れやにじみ
- 定期的なオイル交換の記録があるか
エンジンをかけてみて、「ガラガラ」といった異音がないか、マフラーから異常な色の煙が出ていないかを確認しましょう 。
エンジンルームを見て、オイルが漏れている箇所がないかも重要なチェックポイントです。
修復歴の有無と車両の使用歴を確認する
車両の骨格部分(フレーム)を修理した「修復歴」のある車両は、走行安定性に問題がある可能性があるため、避けるのが賢明です 。
また、そのトラックがどのような環境で使われてきたか(使用歴)も、劣化具合を判断する上で参考になります。
- 修復歴の有無を販売店に必ず確認する
- 過積載が多いダンプなどはフレームへの負担が大きい
- 沿岸部や降雪地域で使われた車両は錆に注意
例えば、建設現場で使われていたダンプは、過酷な環境でフレームに大きな負担がかかっている可能性があります 。
車体の下回りを覗き込み、錆や腐食が進んでいないかもしっかりと確認しましょう。
試乗して走行フィーリングを確かめる
可能であれば、必ず試乗させてもらい、実際に運転した感覚を確かめることが大切です 。
エンジンをかけただけではわからない、トランスミッションや足回りの不具合を発見できることがあります。
- 変速時のショックが大きすぎないか
- 走行中に異音や異常な振動はないか
- ブレーキがしっかりと効くか
特に、デュアルクラッチトランスミッション「DUONIC(デュオニック)」搭載車は、その作動フィーリングに癖があるため、自分の感覚に合うかを確認しておきましょう。
まっすぐ走るか、ハンドルがぶれないかといった基本的な走行性能も、試乗でなければわかりません。
よくある質問|三菱ふそうのキャンターは「故障が多い」「壊れやすい」のか徹底解説
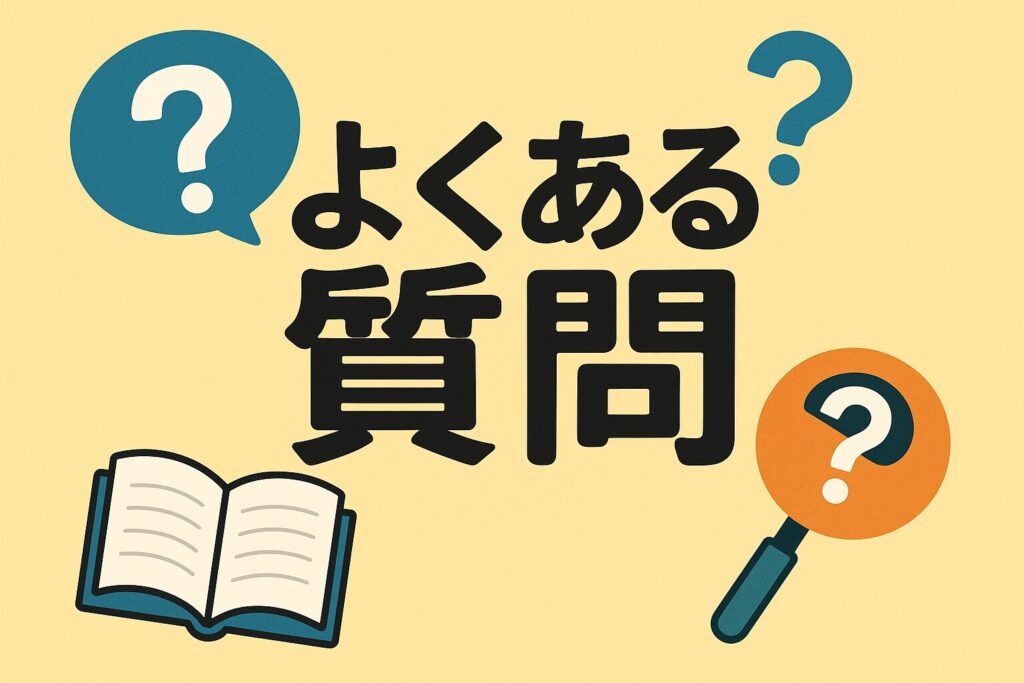
ここでは、三菱ふそうのキャンターに関してよく寄せられる質問にお答えします。
- 壊れやすい年代はある?
- 4P10エンジンの故障はリコール対象?
- インジェクターの交換費用は?(概算)
- キャンターが安い理由は?
- キャンターと「エルフ」どっちがいい?
- 新型キャンターの悪いところは?
- 三菱ふそうは故障が多い?
これらの疑問を解消し、キャンターへの理解をさらに深めていきましょう。
壊れやすい年代はある?
はい、特に壊れやすいとされる年代は存在します。
具体的には、4P10型エンジンが初めて搭載された2010年(平成22年)以降の第8世代モデル、通称「ブルーテックキャンター」で故障の報告が多くなっています 。
- 2010年〜の第8世代モデル
- 排出ガス浄化装置(DPF, 尿素SCR)関連のトラブル
- 燃料ポンプの接触不良など電気系統の不具合
この時期のモデルは、新しい排出ガス規制に対応するための複雑なシステムを初期に導入したため、トラブルが多発しました 。
特にダンプ仕様車では、車体の振動が原因で燃料ポンプのハーネスに不具合が出やすいという指摘もあります 。
4P10エンジンの故障はリコール対象?
はい、4P10エンジンに関連する不具合で、過去に複数のリコールが届け出られています。
ただし、全ての故障がリコール対象となるわけではありません。
- ロッカーアームの耐久性不足(2019年)
- ブローバイガス還元装置の不具合(2018年)
- 機械式自動変速機の制御プログラム(2018年)
リコールは、あくまで設計・製造過程に起因する特定の不具合に対して行われる無償修理制度です 。
経年劣化やメンテナンス不足による故障は対象外となるため、注意が必要です。
インジェクターの交換費用は?(概算)
インジェクターの交換費用は、部品の種類(新品かリビルト品か)や本数、整備工場の工賃によって大きく変動します。
一般的に、4本のインジェクターを新品に交換する場合、総額で20万円から30万円以上かかることも珍しくありません 。
- 新品インジェクター:1本あたり約6万円〜7万円
- リビルトインジェクター:1本あたり約2万5千円〜4万円
- 交換工賃:数万円〜
費用を抑えたい場合は、品質が保証されたリビルト品(再生部品)を活用するのが有効な手段です 。
リビルト品であれば、部品代を新品の半額以下に抑えられる可能性があります。
キャンターが安い理由は?
中古車市場でキャンターが同年代のライバル車に比べて安価で販売されている場合、いくつかの理由が考えられます。
最も大きな理由は、やはり「故障が多い」というイメージが市場価格に反映されていることです。
- 4P10エンジン搭載モデルの故障リスク
- 修理費用が高額になる可能性への懸念
- 過去のリコール問題によるブランドイメージ
特に4P10エンジン搭載モデルは、購入後の維持費がかさむリスクを考慮して、敬遠するユーザーも少なくありません 。
そのため、買い手がつきにくく、結果として販売価格が抑えられる傾向にあります。
キャンターと「エルフ」どっちがいい?
キャンターといすゞ「エルフ」は、小型トラック市場における長年のライバルであり、どちらを選ぶべきかは一概には言えません。
一般的に、信頼性や維持費の安さを重視するならエルフ、パワーや先進装備を求めるならキャンター、という評価が多いようです。
- エルフ:信頼性が高く、燃費が良い傾向
- キャンター:エンジンパワーが力強い、先進安全装備が充実
- 乗り心地や運転感覚は個人の好みによる
エルフは堅実な設計で故障が少ないと定評があり、燃費性能も優れています 。
一方、キャンターは力強い走りが魅力で、衝突被害軽減ブレーキなどの安全装備をいち早く導入してきました。
新型キャンターの悪いところは?
現行の新型キャンター(第9世代)は、第8世代で問題となった点の多くが改善されていますが、オーナーからはいくつかの点が指摘されています。
特に、デュアルクラッチ式トランスミッション「DUONIC」のギクシャクした変速フィールを挙げる声が見られます 。
- DUONICの変速タイミングが不自然に感じることがある
- エンジン音やキャビン内の騒音が気になるという意見も
- 低速トルクが細いと感じる場面がある
また、エンジン音の大きさや、坂道発進時のトルク不足感を指摘するレビューもあります 。
これらの点は、ドライバーの好みや運転スタイルによって評価が分かれる部分といえるでしょう。
三菱ふそうは故障が多い?
「三菱ふそう」というブランド全体が故障が多いというわけではありません。
過去のリコール問題などからネガティブなイメージを持つ人もいますが、大型トラック「スーパーグレート」などは高い評価を得ています。
- キャンターの特定のモデルで故障が多発した
- 他メーカーのトラックにも固有の弱点は存在する
- 定期的なメンテナンスが重要である点は全メーカー共通
キャンターの評判も、問題が集中した4P10エンジン搭載の第8世代モデルによる影響が大きいといえます 。
どのメーカーのトラックであっても、定期的なメンテナンスを怠れば故障のリスクは高まります。
まとめ|三菱ふそうのキャンターは「故障が多い」「壊れやすい」のか徹底解説

本記事では、三菱ふそうのキャンターが「故障が多い」「壊れやすい」といわれる理由について、徹底的に解説しました。
- 故障の真偽:評判は事実だが、主に2010年以降の「4P10エンジン」搭載モデルに問題が集中している。
- 故障の背景:厳しい排出ガス規制に対応するための複雑なエンジンと浄化装置が原因。
- 主な故障:エンジンストール、DPFの詰まり、インジェクターの不具合が代表的なトラブル。
- 修理費用:エンジン載せ替えで100万円超えも。DPFやインジェクターの修理も高額になる傾向。
- 対策:DPFに優しい運転を心がけ、適切なオイル管理を行うなど、日常メンテナンスでリスクは低減できる。
- リコール:ブレーキやエンジン部品などで過去に大規模なリコールが実施されている。
- 売却か修理か:修理費と市場価値、今後の使用計画を天秤にかけて判断することが重要。
- 高価売却の可能性:10年落ちでも海外需要により、予想以上の高値で売却できる可能性がある。
- 中古車購入の注意点:エンジンの状態確認と試乗は必須。修復歴や使用歴も要チェック。
キャンターの故障に関する不安は、その原因と対策を正しく知ることで、大きく軽減できます。
この記事で得た知識を活かせば、問題を未然に防ぎ、万が一の際にも冷静に対処できるはずです。
そして、もし売却を検討する際には、その価値を最大限に引き出すことができるでしょう。
あなたのキャンターが、ビジネスの頼れるパートナーとして、これからも活躍し続けることを願っています。
\損する前にご相談を/
修理不要|トラック高価買取専門店おすすめ
| おすすめ トラック買取専門店 | |
|---|---|
1位.トラックファイブ \創業22年の大手/ 今すぐ無料査定 | ◆ 圧倒的な高価買取 直営店で中間マージンなし。海外販路が強く円安効果も反映 ◆ 国内大手の信頼 年間買取13,000台以上。リピート率47.2% ◆ スピード対応 最短即日現金化も ◆ どんな車も査定OK 低年式、不動車、故障車も対応 ◆ 安心のサポート 面倒な書類手続きもすべて無料で代行 |
2位.Bee Truck \プロの加点査定/ 今すぐ無料査定 | ◆ 直販型で高価買取 整備から販売まで自社完結。オークション任せにしない ◆ 独自の加点査定 業界歴20年以上の査定士が担当。他社が見落とすポイントも徹底評価 ◆ 再生し価値アップ 自社整備工場で修理・塗装。原価以上の価値を生み出す ◆ 他社見積り歓迎 比較前提の戦略で1円でも高く買取り |
3位.トラック王国 \満足度93%/ 今すぐ無料査定 | ◆ 現地での減額なし 電話ヒアリングと相違なければ、査定額を保証 ◆ お客様満足度93% 創業17年の実績 ◆ 最短即日現金化 会社の運転資金ニーズにも対応 ◆ 柔軟な要望に対応 「社名ペイントをすぐ消してほしい」「書類手続きを代行してほしい」など ◆ 高い知名度 見たことある安心感 |
査定額は1社ごとに全く違います。何十万円も損しないためにも、3社査定をしましょう
